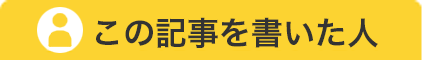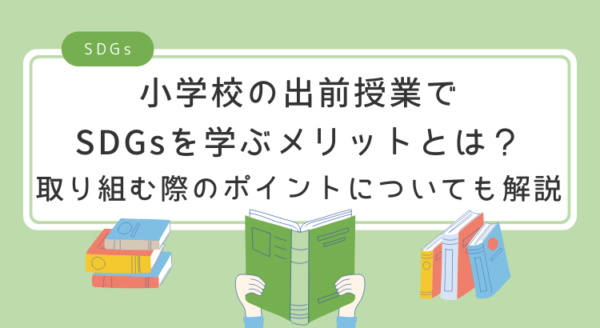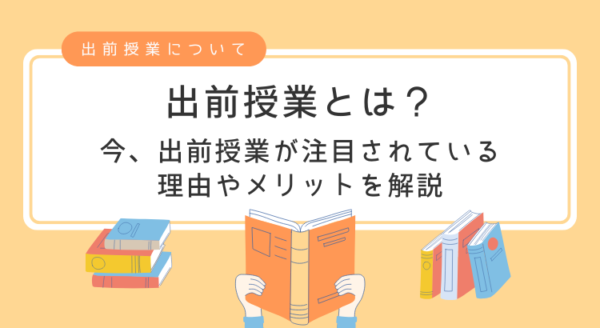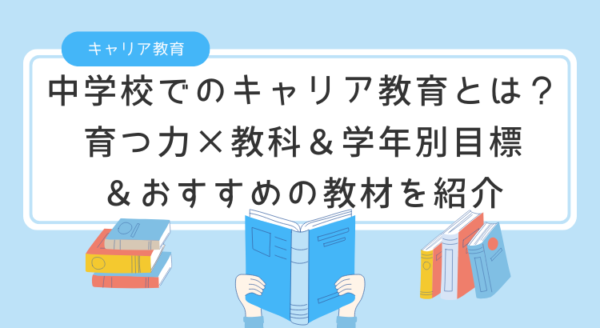
中学生になると、体も心も少しずつ大人に近づき、個性や考え方がだんだんと形作られてきます。
しかし、高校入試の進路選択が間近にあり、数年後には働き始めるのだという実感はあまりない子がほとんどでしょう。
「働く意義をどのように伝えたらいいのか」
「自分なりに進路について考えさせるにはどうしたらいいのか」
中学生という多感な時期だからこそ、個性や適性を大切にしながら、将来について考えさせたいと思う先生は多いことでしょう。
今回は、中学校で行われるキャリア教育について、どんな教育が行われているのか、育てていきたい力や学年別の目標と実践場面を説明します。
最後には、キャリア教育に適した方法もご紹介していきます。
中学校でのキャリア教育の実践に悩んでいる方は参考にしてみてください。
中学校で教えられるキャリア教育とは
子どもたちが育っている社会環境が大きく変わってきたことによって、子ども達は人間関係を上手く構築できなかったり、自分で意思決定をできなかったりする傾向があります。
自己肯定感の低い子は将来に希望が持つことができず、自立した社会人としての基盤に欠けます。
また、社会でも産業・経済の構造的変化によって、入社時から優秀な人材を採用したいという風潮が高まっています。
こうした影響から現在のキャリア教育は、未就学児から継続的に取り組まれています。
ここでは、詳しい目標や内容、課題を説明します。
中学校におけるキャリア教育の目標
平成23年「中学校 キャリア教育の手引き」によると、中学校におけるキャリア教育の目標は、以下の4つとされています。
- 肯定的自己理解と自己有用感の獲得
- 興味・関心等に基づく勤労観・職業観の形成
- 進路計画の立案と暫定的選択
- 生き方や進路に関する現実的探索
小学校段階の目標よりも、職業を現実的に探したり、選択したりする目標になっています。
実際に選択していかなければいけない高校生の時期も踏まえて、系統性が意識されています。
参考:キャリア教育の目標と意義
中学校におけるキャリア教育の内容
中学校におけるキャリア教育は、時間数や教科は決められていないため、地域や学校の特色、生徒の実態を踏まえて内容を検討する必要があります。
保護者や生徒を対象にしたアンケート調査などを基にして、学校全体で目指す生徒像を明確にすることで、キャリア教育で養いたい資質・能力・態度が見えてきます。
キャリア教育の全体計画が定まることで、学年ごとに足並みをそろえた学習内容を決めることができます。
中学校におけるキャリア教育の課題
中学校では、キャリア教育を推進する上で、「職業体験の充実」に取り組む学校が多くあります。
職業体験活動を中学2年生で行う学校は、全体の約9割を占めます。
しかし、キャリア教育は中学2年生の1年間だけ集中して取り組めばよいものではありません。
中学校3年間でのキャリア教育を通して、段階的に生徒の資質・能力・態度を育む必要があります。
職場体験活動に限らず、中学1年生や3年生も含めて、生徒の実態に合わせた系統性のある取り組みが、今後ますます求められます。
参考:中学校におけるキャリア教育の現状と課題
中学校のキャリア教育で育つ力
キャリア教育によって育つ力は、もともと「4領域8能力」と呼びならわされてきました。
しかし、平成23年に中央教育審議会から出された答申によって、4つの能力によって構成される「基礎的・汎用的能力」という観点が新しく示されました。
現在の中学校では、「基礎的・汎用的能力」を育てるキャリア教育が進められています。
ここでは、「基礎的・汎用的能力」を構成する4つの能力について、各教科との関連を説明します。
参考:中学校における「基礎的・汎用的能力」の育成
人間関係形成・社会形成能力
人間関係形成・社会形成能力の育成は、「自己と他者」「集団、社会」を意識した視点が必要となります。
他者の理解と尊重、多様な他者と協働するにはチームワークやコミュニケーション力を必要とするため、教科と関連付けられる要素が多いという特徴があります。
・国語
生徒の言語に対する関心や理解を深めることで、コミュニケーションの基盤である言語の能力を培います。
・保健体育
運動やスポーツを通して、ルールやマナーについて合意したり、適切な人間関係を築いたりして社会性を高めます。
自己理解・自己管理能力
自己理解・自己管理能力は、社会と自分の相互関係について知ることの重要性を意識した視点が必要です。
特に自分を律したり、研鑽したりする力は自己管理能力にとって大事な要素です。
・音楽
曲想を感じ取る活動を通して、生徒一人一人がイメージや感情を意識することができるようになり、自己理解を深めることができます。
・美術
表現や鑑賞の幅広い活動を通して、創造活動に夢中になって取り組む経験をすることができます。
これは、自分を研鑽し、よりよいものを生み出したいという感情や主体的な態度の育成につながります。
課題対応能力
課題対応能力は、情報の理解・選択・処理だけでなく、課題の本質を理解し、原因の追究も行う力が求められます。
課題を発見し、計画を立て、実行し、評価・改善する要素もあり、情報機器を活用する力も含みます。
・数学
図形を操作したり、観察したりして実験する学習では、不思議に思うことや疑問点を整理し、解決のための見通しをもって答えを出そうとします。
問題解決的な学習は、既に持っている知識や情報手段を上手く使って課題に取り組む力となります。
・外国語
インターネットで情報を得たり、メールで発信したりする学習は、世界と主体的に関わろうとする態度と同時に、正しい情報モラルをもってコンピュータを扱う力も育んでいます。
キャリアプランニング能力
キャリアプランニング能力は、「働く」ということを意識して、将来について「考える」「実践する」「学ぶ」「選択する」ことを求められる力です。
自分の将来設計をすることに直接的に関係する力だと言えるでしょう。
・社会
市場経済の基本的な考えについて理解させる学習では、自分なりに働くことを意識した上でお金の流れや自分の行動を考え、将来について模索します。
・理科
授業の中には、地震や天気などの自然科学に関する職業や、新しい科学技術に関する職業が多く紹介されます。
生徒は、理科的事象に関する仕事を選択肢として視野に入れることができます。
中学校の学年別キャリア教育の目標と実践場面
中学校では、1・2・3年生とそれぞれの学年で段階を踏みながらキャリア教育を学びます。
ここでは、学年別の目標例と実践場面を紹介します。
参考:中学生におけるキャリア教育
中学1年生
目標例
- 自分のよさや個性が分かる。
- 自己と他者の違いに気付き、尊重しようとする反面、自己否定などの悩みが生じる。
- 集団の一員としての役割を理解し、それを果たそうとする。
- 将来の職業生活との関連の中で、今の学習の必要性や大切さを理解しようとする。
- 学習の過程を振り返り、次の選択場面に生かそうとする。
- 将来に対する漠然とした夢や憧れを抱いている。
中学1年生は、入学後に自分のよさを見つけられなかったり、前向きに捉えられなかったりする傾向があります。
中学2年生
目標例
- 自分の言動が、他者に及ぼす影響について理解する。
- 社会の一員としての自覚が芽生えるとともに、社会や大人を客観的に捉えるようになる。
- 体験等を通して、勤労の意義や働く人々の様々な思いが分かる。
- よりよい生活や学習、進路や生き方等を目指して自ら課題を見出していくことの大切さを理解する。
- 将来への夢を達成する上での現実の問題に直面し、模索する。
中学2年生は、中学校生活の折り返し地点を迎え、進路の選択を考えなくてはいけない時期です。
総合的な学習の時間を活用して、職場体験活動を行う実践があります。
この実践は、探究的な学習に位置付けることで、自分事として調べ、自分ならどんな働き方をするか考えることができます。
社会的・職業的な自立に向けて自己理解を深めるきっかけになるでしょう。
中学3年生
目標例
- 自己と他者の個性を尊重し、人間関係を円滑に進めようとする。
- 社会の一員としての参加には義務と責任が伴うことを理解する。
- 係・委員会活動や職場体験等で得たことを、以後の学習や選択に生かそうとする。
- 課題に積極的に取り組み・主体的に解決していこうとする。
- 将来設計を達成するための困難を理解しそれを克服するための努力に向かう。
中学3年生は、進路の決定がゴールになってしまいがちな時期です。
特別活動の時間を活用し、これまでの成長を振り返って、未来の自分に手紙を書くという実践があります。
この実践では、小学校からのキャリア・パスポートや、保護者からの手紙を読んで、これまでの自分の成長や変容に気づき、さらに16歳の自分の姿を考えます。
進路選択について考える機会となり、キャリアプランニング能力を身に付けることができるでしょう。
中学校でキャリア教育をする際のポイント
中学でキャリア教育をする際に気を付けたい3つのポイントがあります。
職場体験の内容を充実させる
職場体験は、中学校の生徒にとって、実社会との初めての出会いの場です。
働くことの達成感ややりがいを感じることができ、自分自身についても理解を深められるチャンスと言えるでしょう。
国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターが公表した「平成31年度職場体験・インターンシップ実施状況等調査」では、公立中学校での職場体験は、97%も実施されていることが分かっています。
しかし、5日間の実施を行っている中学は減少傾向にあり、短期間の体験で終わりがちになっています。
生徒にとって充実した職場体験にするためには、内容と日数をできるだけ多く確保できるようにする必要があります。
多様な体験活動の実施
キャリア教育の体験は、企業での仕事に限りません。
ボランティア活動や地域貢献活動などを通しても、働く喜びや人の役に立てた達成感を味わうことができます。
一人一人のキャリアには、仕事以外にも軸となるものがあって良いのだということを生徒に知らせる上で、多様な体験活動を取り入れることは大切です。
個人に合わせて丁寧なキャリアカウンセリングを行う
中学生の進路についての悩みは多岐にわたります。
進路相談のチャンスはあっても、十分に対応できないことがあります。
大人が個々の興味関心に合わせて、個別に丁寧な指導を行うことが必要です。
教員だけでなく、カウンセラーやキャリア教育コーディネーターなどの専門家の力を借りながら、支援体制を強化しましょう。
中学校でのキャリア教育に適した方法
中学校では、大きく分けて3つの教材を用いて、キャリア教育を行うことができます。
企業の社員が語る生の声を聞かせる
一つ目は、社員が学校に講師として来校し、直接生徒に語る生の声を聞かせるという方法です。
生徒達は、普段の先生とは違う大人が語る言葉にいつもより集中して聞く場合もあります。
思春期になると、日常生活で関わる親や先生の言葉にはなかなか耳を傾けなくなるものですが、第三者の言葉には耳を傾けたり、心に強く響くことがあります。
仕事の内容だけでなく、就職のきっかけや、働いて感じるやりがいなどについても話してもらえると、生徒はイメージが湧きやすくなります。
ワークシートや製品の実物を提示する
二つ目は、企業が無料で提供するワークシートや製品を利用する方法です。
企業によっては、授業パッケージを用意しているところもあり、ワークシートや製品を用いながら、担任が授業を行うことができます。
企業ならではの工夫が凝らされた内容なので、多くの生徒が興味をもつでしょう。
また教師主導のため、ワークシートをもとにグループワークをさせたり、課題解決を進めたりといったアレンジが可能です。
生徒の実態に合わせて、製品の実物に触れる時間を長く取り、感想を共有するなどのアレンジが容易にできます。
職業体験・企業訪問を行う
三つ目は、学校を出て行う職業体験・企業訪問です。
事前学習や事後学習も含めて、生徒にとって一度しかないチャンスです。
勤労観を養う上で、とても良い教材となるでしょう。
特に事後学習で自分のこれからの職業選択にどんな影響を与えるかを考えさせることが大切です。
体験して終わりではなく、体験を活かして自分がどのようにキャリアを描いていくのかまで指導していく必要があります。
まとめ
今回は、中学校で行われるキャリア教育について、目標・内容・課題について触れ、育つ力と教科の関係を説明しました。
中学校でのキャリア教育は、時間が取りづらいと言われる中でも、教科との関連付けによって、キャリア教育の機会は増やすことができます。
学年別にもそれぞれ、キャリア教育の目標をもつことで、小学校を卒業したばかりの中学1年生から、進路の選択を迫られる中学3年生まで、段々と成長していくことができます。
最後にご紹介したキャリア教育に適した方法は、【出前授業どっとこむ】で簡単に検索することができます。
中学生向けのキャリア教育の場合、対象学年を【中学生】に設定し、こだわりの条件でテーマ【キャリア】、キーワード【教材提供】などと検索することで、簡単に企業が提供している授業を知ることができます。
これからキャリア教育の授業を検討している方は、まずはどのような出前授業があるのか検索してみましょう。