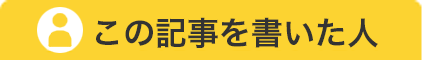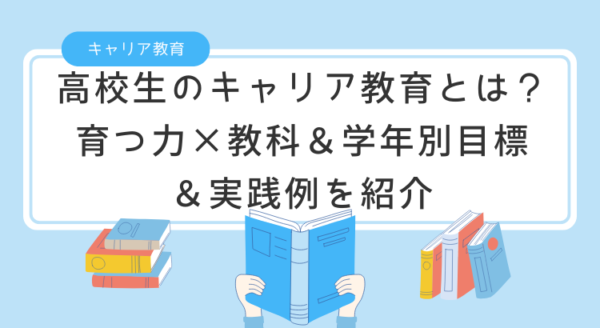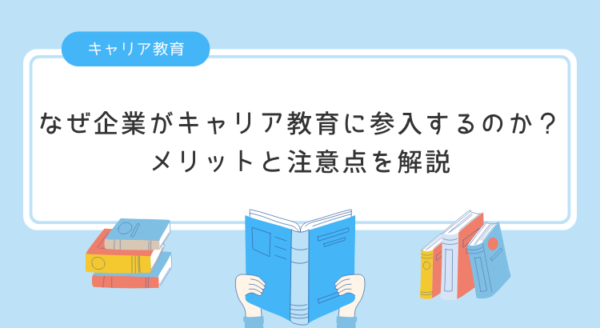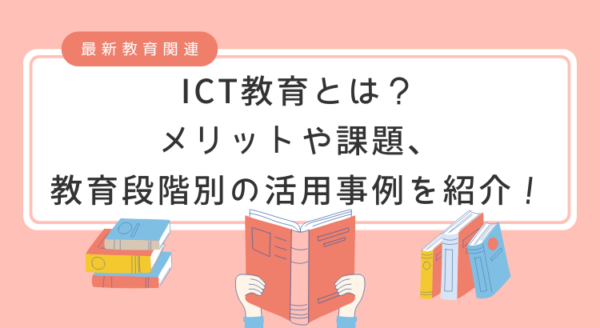
ICT教育とは、パソコンやタブレットなどの電子機器を活用した教育方法です。
ICT教育を導入すると、効率的に授業を進められることやクラス全員参加型の授業ができるなどのメリットが得られます。
一方で、端末購入による経済的負担や機器の故障対応など、課題があることも事実です。
今回は、ICT教育のメリットや課題、教育段階別の活用事例をご紹介します。
ICT教育の対応方法を理解したい教育関係者は、ぜひ参考にしてください 。
ICT教育とは?
ICT教育とは、パソコンやタブレットなどの電子機器を活用した学習効率を高めるための教育方法です。
ICT教育には、以下の3つの目的があります。
- 情報活用能力の育成
- 教科指導におけるICT活用の推進と教員の指導力向上
- プログラミング教育の実施に向けた取組
デジタル社会への対応力の育成は、将来社会で子どもたちが活躍するために大切です。
例えば、基本的なデジタル機器の操作スキルやオンラインでのコミュニケーション能力を培えば、子どもたちの職業選択の幅が広がります。
また、緊急時の学習継続に対応するためにICT教育は必要です。
もし、再び新型コロナウイルスの感染が拡大した場合にICT教育を進めておくと、スムーズにオンライン授業を進められます。
ほかにもICT教育では、子どもたちへ主体的な参加を促す双方向型やそれぞれの生徒のペースに合わせた授業など新たな学習スタイルを確立する目的があります。
ICT教育のメリット
ICT教育には、主に教員目線で4つのメリットがあります。
- 効率的に授業を進められる
- クラス全員参加型の授業ができる
- 児童生徒の理解度に合わせて復習や個別指導ができる
- 教員の負担を軽減できる
ICT教育のメリットを把握すれば、効率的に児童生徒の関心を惹く授業を進めることが可能です。
それぞれのメリットを理解しつつ、ICT教育の対応方法に関して理解を深めてください。
効率的に授業を進められる
ICT教育では映像や音声、アニメーションなどを用いて授業が行われるため、わかりやすいところが特徴です。
例えば、図形問題では実際に図形を動かしながら解説できるため、視覚的に深い理解ができます。
また、教員が書き込んだ授業の解説がタブレットにも共有されるため、一度で吸収できなかったところも見返すことができます。
このように授業がわかりやすくなれば、生徒たちもストレスなく勉強を進めることができるでしょう。
クラス全員参加型の授業ができる
ICT教育では、クラス全員参加型の授業が可能です。
タブレットを活用することで、グループごとに意見交換ができ、子どもたちの主体的な学びを促せます。
また、ICT教育では、タブレットを活用して授業で学んだことについて資料を作成し、グループごとの意見交換ができます。
能動的に授業へ取り組むため、内容を理解しやすくもなります。
児童生徒の理解度に合わせて復習や個別指導ができる
ICT授業のメリットとして、児童生徒のレベルに合わせた復習や個別指導ができることがあげられます。
例えば個別学習する場合は、間違えた問題の復習ができるため、同じ間違えをしない対策が可能です。
また、個人が取り組んだ問題や内容、進捗状況が残るため、得意項目や苦手項目などが理解できて適切な指導ができます。
個人に適切な指導をすれば学習へのモチベーションが高まり、自主的に自己学習する機会が増えるでしょう。
教員の負担を軽減できる
ICT教育の推進は、教員の負担軽減にもつながっています。
従来の教育現場は手書きの書類が多く、手作業の業務が教員の負担増加になっていました。
しかし、ICT教育を導入すれば紙でプリントを印刷して配布する時間の短縮や、インターネットを活用して素早い教材の作成が可能です。
授業の準備時間を短縮すれば、さらに魅力的な授業内容を考えることや新しい取り組みを考えられます。
教員の負担軽減は、授業の質を向上させることにつながっています。
ICT教育の課題
ICT教育にはメリットだけでなく、3つの課題もあります。
- 端末購入による経済的な負担(高校のみ)
- 児童や生徒へのITリテラシー習得のための指導
- 機器の管理と故障対応
ICT教育の課題を理解することで、導入時の準備や対策を講じやすくなります。
それぞれの課題を参考に、ICT教育の課題に関して理解を深めましょう。
端末購入による経済的な負担 (高校のみ)
ICT教育では、義務教育ではない高校では、端末購入による経済的な負担をしなければなりません。
ICT教育を実現するためには、児童全員にタブレット端末を準備しなければなりません。
文部科学省によると、2022年末時点で義務教育では、99.9%の児童生徒に端末が行き渡っていることが明らかになっています。
参考:文部科学省|義務教育段階における1人1台端末の整備状況
公立高校においても、多くの学校でタブレット端末が整備されています。
しかし、費用は学校が負担している場合や保護者が負担している場合などさまざまです。
参考:文部科学省|高等学校段階における学習用端末の整備状況について
保護者の中には、端末費用を負担することに不満を感じる人が一定数いるかもしれません。
事前に保護者へアンケート調査をし、端末購入に対する意向を確認してください。
なお、義務教育である小中学校と高校ではICT教育の導入具合が異なっている点も、改善しなければならない課題です。
児童や生徒へのITリテラシー習得のための指導
ICT教育では、児童や生徒へのITリテラシー習得のための指導をしなければなりません。
多くの学校では外部リンクにアクセスできないようにセキュリティ対策が行われています。
しかし、ICT教育が進むと自由に使いこなせる子どもが増加するでしょう。
例えば、投稿した写真で個人を特定されたり、他人にIDとパスワードを教えてアカウントを乗っ取られてしまったりするリスクなどが考えられます。
児童や生徒の安全を守るためには、タブレットでインターネットを活用するリスクや禁止事項を伝えておき、トラブルを未然に防ぐ指導が必要です。
機械の管理と故障対応
ICT教育をする際は、機械の管理と故障対応に対して事前に考えておかなければなりません。
端末の管理は、学校で管理する場合と個人に管理を任せる方法があります。
学校で管理をすると子どもたちは自由学習に活用しにくくなるためスキルを向上しにくいです。
ただ、学校で管理すれば端末が故障しにくくなります。
児童生徒に管理を任せると好きな時間に自由学習できるため学力を高めやすいですが、破損リスクや自宅に忘れるリスクがあります 。
ほかの教員と相談したうえで、タブレット端末の管理方法を決定しましょう。
ICT教育の活用場面
ICT教育では、以下の6つのような活用ができます。
- インターネットを用いた情報収集
- インターネットを活用した資料や作品の制作
- グループやクラス全体での発表・話し合い
- 複数人の意見や考えを議論して整理
- グループでの役割の分担・一緒に作品の制作
- 遠隔地や海外の学校との交流
上記の内容を参考にしつつ、ICT教育を活用して効率的に授業を進めていきましょう。
出前授業を利用してICT教育を進めよう
ICT教育を導入すると、児童生徒の理解度に合わせた復習と個別指導が可能です。
また、教員の負担軽減といったメリットも得られます。
一方で、端末が揃っていたとしてもWi-Fi環境が整っていなくて通信制限がかかる場合や、教員へITリテラシーに関する指導をしなければならないなどの課題もあります。
本記事でご紹介した内容を参考にし、ICT教育を導入すべきか判断してください。
出前授業どっとこむでは、児童・生徒のためになる授業を数多く用意しています。児童・生徒へ学校の授業とは違う授業を受けさせたいとお考えの方は、出前授業どっとこむにお問い合わせください。