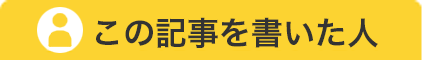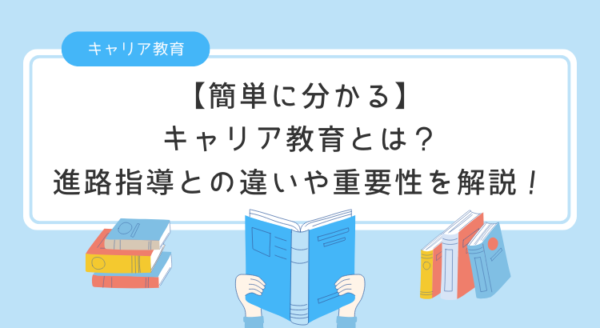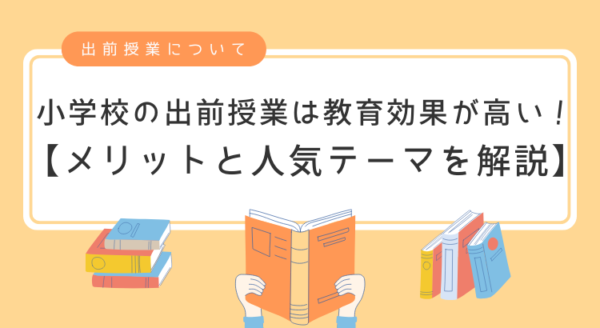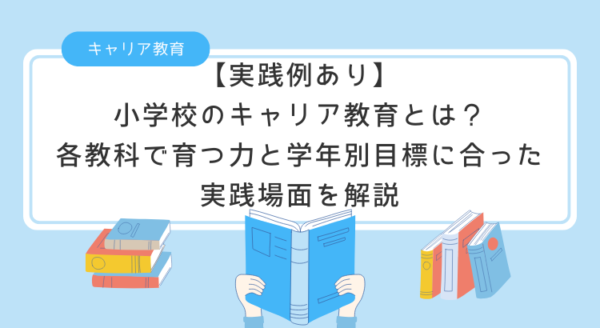
昨今、小学校段階からキャリア教育が行われることは当たり前になってきました。
「小学校でのキャリア教育って何をすればいいの?」
「キャリア教育を小学生にするなんて、時期が早いのでは?」
キャリア教育を受けていない大人の多くは、どのような授業をしたらいいのか悩んでしまいます。
今回は、小学校でのキャリア教育に焦点を当て、キャリア教育とは何か、育つ力や目標を具体的な場面を挙げながら分かりやすく解説します。
小学生に向けたキャリア教育を検討している方は参考にしてみてください。
小学校で教えられるキャリア教育とは
現在、小学校で教えられているキャリア教育は、教科や授業時間数を明確に決められていません。
また、各地域の小学校によって内容が異なり、学年ごとの子どもの実態を把握し、キャリア教育によって育成すべき能力や態度を決定します。
小学校の学区域によっては、商店街が身近にある地域や、自然や農林水産業が身近な地域などさまざまな性格があります。
キャリア教育は地域資源を活用した形での取り組みが推進されているため、内容はそれぞれの小学校の裁量に任せられています。
そのため、これからご紹介する定義づけや導入の背景を踏まえて、小学校ごとに実情に応じた教育活動が求められています。
キャリア教育の定義
キャリア教育は「児童生徒一人一人のキャリア発達を支援し、それぞれにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能力を育てる教育」と定義されています。
簡単に言うと子どもたち一人一人の勤労観や、職業観を育てる教育です。
必ずしも職場体験などの体験活動を取り入れる必要はありません。
日々の教育活動をキャリア教育の視点から捉えなおして、取り組むことができます。
参考:国立教育政策研究所|小学校におけるキャリア教育をめぐる9つの疑問にお答えします
小学校にキャリア教育が導入された背景
現在のキャリア教育は、未就学児や小学校段階から取り組むことが推奨されています。
これは幼い時から、さまざまな職業の存在を知ることで、職業に対して広い視野をもつことができるからです。
平成20年度に実施された「全国学力・学習状況調査」では、「将来の夢や目標を持っていますか」という質問に対して、小学生の約68%が「当てはまる」と回答しました。
一方で、中学生は約43%となり、25%の差がありました。
これは中学生になり、心身が成長することで、小学生の時に思い描いていた夢を描き続けられなかったり、次の目標が見いだせなかったりすることが原因であると考えられます。
小学校から継続的にキャリア教育に取り組むことで、子どもたちは成長して夢が変わっていっても、自分の将来につながる希望や目標を描くことができるようになります。
子どもの成長を見通したキャリア教育は、将来設計の力を育むという考え方から、キャリア教育は小学校段階でも導入されています。
参考:
教育課程実施状況調査(小学校第5学年)
教育課程実施状況調査(中学校第2学年)
小学校のキャリア教育の内容
小学校で行われるキャリア教育の内容は、各地域の小学校によって内容が異なります。
学年ごとの子どもの実態を把握し、キャリア教育によって育成すべき能力や態度を決定します。
小学校の学区域によっては、商店街が身近にある地域や、自然や農林水産業が身近な地域などさまざまな性格があります。
キャリア教育は地域資源を活用した形での取り組みが推進されているため、内容はそれぞれの小学校の裁量に任せられています。
小学校のキャリア教育で育つ力
キャリア教育によって育つ力は、もともと「4領域8能力」と呼びならわされてきました。
しかし、平成23年に中央教育審議会から出された答申によって、4つの能力によって構成される「基礎的・汎用的能力」という観点が新しく示されました。
現在の小学校では、「基礎的・汎用的能力」を育てるキャリア教育が進められています。
ここでは、「基礎的・汎用的能力」を構成する4つの能力について、各教科との関連を説明します。
人間関係形成・社会形成能力
・社会科
社会生活についての理解を深め、公民的資質の基礎を養うことで、仕事をしていく上での基礎となる力を身に付けることができます。
特に社会科には、キャリア教育と関連付けられる内容が多くあります。
・音楽
合唱や合奏を通して、仲間と協力して一つのものを作り上げる経験ができます。
友達のよさを理解する力や他者に働きかける力は、社会に出ていろいろな人を認めながら、協力して働いていくことにつながります。
自己理解・自己管理能力
・理科
見通しをもって意欲的に観察・実験の活動を行うことで、子どもは主体的な問題解決の経験を積むことができます。
これは、自分の活動の結果を認識できるため、働く上で大切な自分の仕事に対する向上心や探求心につながります。
・体育
サッカーなどのボール運動では、自分の役割を正しく理解して行動する必要があります。
チームで協力する姿勢や、自分の考えや感情を律する力は、仕事をする上での基盤となります。
課題対応能力
・国語
学習過程を明確化することによって、自分から学び、課題を解決できる能力を子どもに身に付けさせるねらいがあります。
これは、仕事をする上で必要な、課題を見つけ、分析し、計画を立てる力につながっていきます。
・算数
知識や技術を学ぶことだけでなく、学んだことを実際の生活の中で生かしたり、計算のきまりを自ら発見したりする学習が重要です。
将来働いた時に、課題を発見・分析したり、処理・解決したりする力の基礎になります。
キャリアプランニング能力
・生活科
小学校低学年の時に、身近な公共施設などで働く人の存在に気付くことで、社会がいろいろな人の支えによって成り立っていることを認識することができます。
このような学習により、将来は自分も社会を支える一員になるのだと、実感を伴って理解することができます。
・家庭科
身近な消費生活の学習では、金銭は働くことによって得られるということや、その大切さを理解することができます。
子ども達もやがては自分も生きていくために働くのだと、将来を見通せる力が身に付きます。
小学校の学年別キャリア教育の目標
小学校6年間でのキャリア教育は、以下のような目標が設定されています。
- 自己及び他者への積極的関心の形成・発展
- 身のまわりの仕事や環境への関心・意欲の向上
- 夢や希望、憧れる自己のイメージの獲得
- 勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の形成
しかし、小学校1年生と6年生では発達段階に大きな違いがあります。
そこで、小学校では、低学年・中学年・高学年という3つの段階に分けて、目標を設定しています。
ここでは、3つの段階ごとに目標としているポイントと具体的な実践場面について説明していきます。
小学1・2年生
“自分の好きなこと、得意なこと、できることを増やし、さまざまな活動への興味・関心を高めながら意欲と自信を持って活動できるようにする”
・日常生活
係や日直など、みんなのために働く活動を通して、働くことの意欲を高めます。
・特別活動
異学年と交流できる機会を通して、一緒に活動する楽しさを経験させたり、助け合おうという態度を育てたりします。
・各教科
自分自身や家族、地域の人に対する関心をもち、自立への基礎を育みます。
・道徳の時間
お話を読み聞かせ、約束やきまりを守ることの大切さを伝えます。
自分のやるべきことは、自分からすすんで行うように促します。
小学3・4年生
“友達のよさを認め、協力して活動する中で、自分の持ち味や役割を自覚することができるようにする”
小学3年生からは総合的な学習が始まるため、キャリア教育を取り入れやすくなります。
・日常生活
給食当番や清掃などの場面では、子ども達がきまりを作り、守ることができるようにします。
・特別活動
学級が一つとなって、取り組める行事に全力で取り組み、協力し合える人間関係を築くことの良さに気づかせます。
また、自発的な活動を尊重することで、人の役に立ちたいという気持ちを育みます。
・各教科
各教科での学びの中で、日常生活や将来の生き方につながることを意識させた授業を展開します。
・道徳の時間
道徳のお話から、身近な人々と協力したり、助け合ったりすることの大切さに気付かせます。
・総合的な学習の時間
探究的な学びを通して、地域の人々の暮らしや生き方を学ぶ機会を設けます。
小学5・6年生
“苦手なことや初めて経験することに失敗を恐れず取り組み、そのことが集団の中で役立つ喜びや自分への自信につながるようにする”
高学年になると、外国語活動の中でキャリア教育を実践することができるようになり、一層学びのチャンスが広がります。
・日常生活
朝の会や帰りの会では、子ども達自身に課題を見つけさせ、解決しようという意識を持たせます。
・特別活動
異年齢集団の活動を通して、高学年としての役割と責任を果たすことができるようにします。
・各教科
学びの中に出てくる生活や職業について理解を深めさせ、子ども同士が学び合ったり、高め合ったりできる授業を展開します。
・道徳の時間
道徳の教材から自己肯定感を育み、将来に対する希望が持てるようにします。
・総合的な学習の時間
地域社会に関わる体験活動を通して、地域と関わることの喜びに気づかせます。
また、探求的な学びを取り入れ、社会の一員としてできることを一人一人に考えさせます。
・外国語活動
日本と外国の言語や文化を比較する活動を通して、多様な物の見方や考え方があることに気づかせます。
出前授業を活用してキャリア教育を実践しよう
各教科との関わりや、具体的な実践場面についてご紹介してきましたが、ここでは、出前授業を活用した小学校でのキャリア教育の実践例をご紹介します。
出前授業の実施形式は大きく以下の3つに分類されます。
- 企業の講師を招く
- 教材提供
- 企業への訪問など職業体験
それぞれ詳しく解説します。
企業の講師を招く
1つ目は、企業や団体から講師として小学校に出張するゲストティーチャーの実践です。
子ども達は、スペシャリストから実際に話を聞くことで、未来に対して希望をもつことができます。
また、学校生活や家庭だけでは見えてこない進路やキャリア・パスに気づくこともできます。
普段、通いなれた小学校に講師を招くため、子どもにとっては安心して落ち着いた環境で話を聞くことができます。
たとえば、ある一般社団法人の出前授業では、専門家による詳しい話だけでなく、共に仕事をする相手の話を聞く機会を設けています。
お互いに違う立場から個性を認め合い、理解し合う大切さを学ぶことでキャリア教育につながるように授業が組み立てられています。
教材提供を活用した実践
2つ目は、講師を派遣せず、企業が提供する授業コンテンツを活用し、先生自身が授業を行う教材提供による実践です。
教材提供の出前授業では、地域の制限もなく、実施日の調整が不要であるものがほとんどなので、子どもたちにより多くの学びを提供することができます。
また、小学生は大人との関わり方に不慣れな部分があるため、外部から講師が来ると緊張してしまったり、内容を正しく理解できなかったりすることがあります。
普段から関わっている学校の先生が、目新しい製品やいつもとは違う流れの授業を行うことで、子どもは安心した中で授業内容に興味をもつことができます。
教材提供の出前授業の中には、自社の製品を小学校に無料で教材として提供している企業もあります。
企業が制作した動画を見ながら、授業を進められるため、教員の授業準備が簡略化されます。
企業への訪問など職業体験
3つ目は、子ども達が学校を出て、実際に職場を訪れて仕事を体験する実践です。
計画や準備の手間がかかりますが、子ども達の記憶に残りやすく、一人一人が働くイメージをもちやすいことが特徴です。
職場体験は特に地域社会と結びつきやすく、地場産業や地域工芸に興味関心をもつきっかけにもなります。
ある農園関係団体は、子ども達に農業体験を提供しています。
子ども達に栽培や収穫を体験させ、環境負荷やフードロスなどの課題を自分ごととして捉えられるようにキャリア教育を支援しています。
まとめ
今回は、小学校でのキャリア教育に焦点を当て、キャリア教育とは何か、小学校のどんな場面で力が育つのか、学年別の目標や実践場面、具体的な授業形式をご紹介しました。
小学校で行われるキャリア教育には、低学年・中学年・高学年でそれぞれの目標はありますが、内容に柔軟性があります。
各小学校が、児童の発達段階や理解度をよく見極め、地域資源を活用してキャリア教育に取り組む必要があります。
キャリア教育は小学校だけでなく、中学校、高校と続きます。
小学生に向けたキャリア教育を検討している方は、対象とする学年の発達段階と、長い期間での子どもの成長を考えて、授業を組み立てていきましょう。
実際に小学校でできるキャリア教育は、出前授業どっとこむの検索機能を用いて調べることができます。
こだわりの条件から【対象の学年】を絞り、【テーマ】でキャリア教育を選択してみましょう。