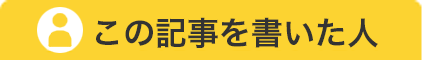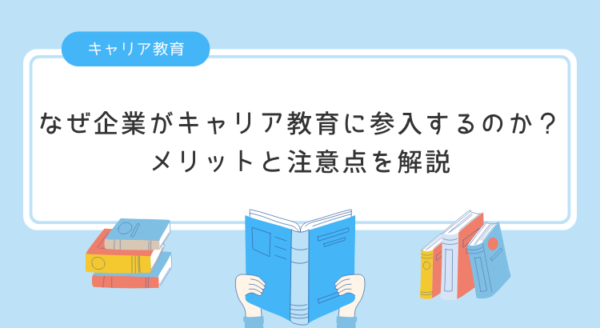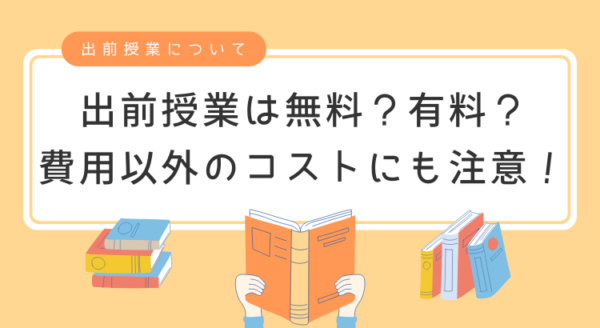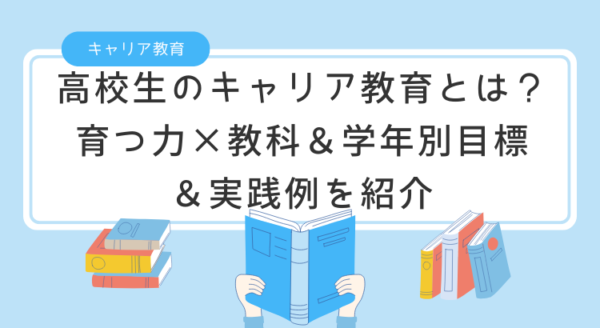
高校生は、中学生のころと比べてさらに独立心や自律の欲求が高まる時期です。
それに伴って、社会に出ることへの不安も感じ始める頃です。
「進路指導以外にキャリア教育は必要なのか」
「キャリア教育はどんな場面で実践されているのか」
高校生と日々関わっている先生でも、キャリア教育について悩んでいる方は多いことでしょう。
今回は、高校生のキャリア教育に焦点を当てて、キャリア教育とはどんなもので、どんな力が身に付くのかを説明していきます。
具体的にキャリア教育が行われる場面や、指導のポイントと実践例もお伝えします。
これから、高校生に向けたキャリア教育を実践する方は参考にしてみてください。
高校でキャリア教育が求められる理由
キャリア教育は、グローバル化によって子どもたちの成育環境が変化したことや、職業界に大きな影響を与えたことを背景にして、平成11年の中央教育審議会答申で初めて提言されました。
キャリア教育によって、未経験の体験に挑戦する勇気とその価値を学ぶことは、自立した社会人になる上で、確かな基盤となります。
しかし、社会環境の大きな変化によって、異年齢との交わりや地域との結びつきの機会が減少したことで、子どもたちの多くは人間関係を上手く構築できなかったり、自分で意思決定をできなかったりする傾向があります。
このような子どもの多くは、自己肯定感が低く、将来に希望が持つことができず、自立した社会人になる基盤が欠けています。
また、社会でも簡単にできる作業は機械化されているため、新入社員の時から複雑な仕事や、人物重視の仕事が任されるように変化しています。
入社時から優秀な人材を採用したいという風潮が高まっています。
こうした影響から現在のキャリア教育は、未就学児から継続的に取り組まれ、各々の発達段階に合わせた「社会人として必要な資質」を身に付ける学習が求められています。
参考:
キャリア教育は生徒に何ができるのだろう?
高等学校におけるキャリア教育
高校で教えられるキャリア教育とは
ここでは、高校で行われているキャリア教育の詳しい目標や内容、課題を説明します。
高校におけるキャリア教育の目標
高校生は、「現実的探索・試行と社会的移行準備の時期」とされ、以下の目標が定められています。
- 自己理解の深化と自己受容
- 選択基準としての勤労観・職業観の確立
- 将来設計の立案と社会的移行の準備
- 進路の現実吟味と試行的参加
高校の段階になると、中学生よりも、より現実的に自分と向き合い、キャリア形成を考えさせるような目標となっています。
小学校・中学校での学びを土台にした系統性のある目標です。
参考:キャリア教育は生徒に何ができるのだろう?
高校におけるキャリア教育の内容
高校でのキャリア教育には、決まった時間数や教科がありません。
各学校が生徒の実態や、高校のある周りの地域経済を踏まえて、育てたい生徒像を決めます。
各学校には、キャリア教育全体計画があり、それをもとに高校生のキャリア課題を解決する授業を行っています。
高校におけるキャリア教育の課題
平成25年の「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査第一報告書」によると、高校の教員の約5割がキャリア教育に関する校内研修に参加したことが無いという結果でした。
高校生の保護者や卒業生は在学中に「就業体験」を行うことを求めています。
しかし、調査では就業体験の日数について、どの学年も「0日」という回答が最も高い結果となりました。
就業体験に対する教員の意識の低さは課題となっています。
また、多くの生徒や卒業生から「就職後の離職・失業など、将来起こりうる人生上の諸リスクへの対応」について「もっと指導してほしかった」という回答がありました。
教員のキャリア教育に対する意識の向上や、転職や離職に関する情報伝達は今後のキャリア教育が行っていくべき課題となっています。
参考:高等学校におけるキャリア教育の現状と課題
高校のキャリア教育で育てたい力
高校でのキャリア教育は、生徒の個性や能力をさらに伸ばし、学校から社会・職業へ移行していく準備をすることが求められています。
キャリア教育では、平成23年に中央教育審議会から出された答申によって、4つの能力によって構成される「基礎的・汎用的能力」を育成するという観点で教育活動が進められています。
ここでは、4つの育てたい力と教科との関わりをご紹介します。
人間関係形成・社会形成能力
人間関係形成は、さまざまな人の考えや立場を理解し、相手の意見を聞いた上で自分の考えを正しく伝える力を示します。
また、社会形成能力とは、自分の置かれている状況を理解し、役割を果たしながら仲間と協力・協働し、積極的に社会を作っていく力を示します。
具体的な要素として、他者の個性を理解する力、他者に働きかける力、コミュニケーション・スキル、チームワーク、リーダーシップなどが挙げられます。
自己理解・自己管理能力
自己理解・自己管理能力とは、自分ができることや、やりたいことを社会との相互関係を踏まえながら、主体的に行動できる力を示します。
また、自分の考え方や感情を律して、これからの成長のために進んで学ぶ力でもあります。
具体的な要素として、自己の役割の理解、前向きに考える力、自己の動機付け、忍耐力、ストレスマネジメント、主体的行動などが挙げられます。
課題対応能力
課題対応能力とは、仕事をしていく上で発生する課題を発見・分析して、適切な計画のもと解決していく力を示します。
具体的な要素として、情報の理解・選択・処理、本質の理解、原因の追究、課題発見、計画立案、実行力、評価・改善などが挙げられます。
キャリアプランニング能力
キャリアプランニング能力とは、働くことの意義を理解し、自分の立場や役割と働くことを関連付けたキャリアを形成していく力を示します。
このキャリア形成には、様々な生き方を知った上で、適切に取捨選択や活用をしながら、自分で判断する力が必要です。
具体的な要素として、学ぶこと・働くことの意義や役割の理解、多様性の理解、将来設計、選択、行動と改善などが挙げられます。
参考:キャリア教育の必要性と意義「キャリア教育とは何か」
高校でキャリア教育が行われる場面
高校でのキャリア教育は、以下の3つの時間を使って実践されます。
- 教科・科目の授業時間
- ホームルーム活動
- 体験活動
それぞれの場面の良さを説明していきます。
教科・科目の授業時間
中学と同様に、高校は科目によって教師が違うため、どの教科においてもキャリア教育の視点をもつ必要があります。
学習の中に出てくる内容が、実社会で活用されていることを分かりやすく伝えることで、学習の面白さや楽しさに気づかせます。
基礎的・汎用的能力を意識した授業づくりによって、キャリア教育とのつながりをもたせることが日常的に可能になります。
ホームルーム活動
ホームルームは、特別活動の中心に位置づけられた時間で、キャリア教育に適した時間です。
学習指導要領では、ホームルーム活動の内容として「一人一人のキャリア形成と自己実現」が明記されています。
ホームルーム活動で重要とされている「合意形成」や「意思決定」を意識した、キャリア教育を実践することによって、生徒の自主的・自発的な学びが期待できます。
具体的には、講師を招いた出前授業や、社会人へのインタビューなどで、クラスメイトと切磋琢磨しながらコミュニケーション能力を高めることができます。
また、一人一人とのキャリアカウンセリングの時間に充てることもでき、継続的に生徒と語り合うことで、生徒との信頼関係を築き支えていきます。
体験活動
体験活動は、日々の学習の意義を再確認できるチャンスです。
具体的には、インターンシップや介護・福祉体験、自然学習など様々な機会があります。
体験活動では、良いことばかりでなく、想像以上に大変であったり、辛かったりすることがあります。
経験したことによって、「知識を身に付けたい!」「もっと上手くなりたい!」という気持ちが芽生え、今後の学ぶ意欲やこれまでの学習経験への気づきにつながります。
また、高校の外に出て、仕事をしているたくさんの人達と関わることで、マナーや言葉遣いに気を付ける機会にもなります。
高校でキャリア教育をする際のポイント
ここでは、社会に出ることが近づいている高校生に対してキャリア教育を行う際のポイントについて、説明します。
社会人・職業人として必要な能力や態度の育成
高校の実態に合わせて、働く上で必要な能力や態度を明らかにしましょう。
これまで十分に意識されていなかったため、改めて学校ごとに到達目標を明確に設定し取り組む必要があります。
「農業科」「商業科」など専門分野のある場合は、モデルを描きやすいですが、「普通科」の生徒ほど明確な目標を教師側でもち、育成していかねばなりません。
労働者としての知識の指導
社会人となる生徒が知っておかねばならない知識を伝えましょう。
労働者としての権利や義務、雇用契約の法的意味などは、公民で学習しますが実際に自分のこととして捉えられない生徒もいます。
求人情報の獲得や人権侵害等への対処など、働く上で困ったことがあった時に相談できる機関についての知っていることは、生徒にとって大きな安心材料になります。
事後活動の充実
高校生へのキャリア教育として、卒業生・地域の社会人や職人達とのインタビューや対話、就業体験活動(インターンシップ)に取り組む学校は多いことでしょう。
大人は、体験の内容を充実させることに注力しがちです。
しかし、体験して終わりにするのではなく、体験によって自分のどんな適性に気づけたのか、将来設計は描けたか、自分の将来と照らし合わせて考えさせる事後活動が大切です。
外部と連携した高校でのキャリア教育実践例
高校で行われるキャリア教育の中でも、生徒にとって記憶に残る授業形式が3つあります。
ここでは、生徒が自分事としてとらえやすい外部と連携して行う3つの授業形式の特徴を説明します。
出前授業のキャリア教育を活用する
まず、外部から講師を招いて出前授業を行う形式です。
ワークシートを講師や教師が作成することで、話を聞くだけでなく自分の考えや、大切だと感じたことを記録することができます。
普段接することのない社会人からの話は、親や教師の言葉よりも素直に受け入れることができるでしょう。
指導案に沿って行う担任による授業
二つ目は、企業が作成した授業プランに沿って授業を行う形式です。
先述の出前授業による講師派遣がコロナ禍でできなくなったことにより、企業が学校向けに授業プランを作って、無料で提供する形が増えました。
教科の学習とは違った生徒の自主性が必要になったり、生徒同士のコミュニケーションが生まれたりする授業の形です。
職場や研究機関の訪問や見学をする体験的な授業
三つ目は、実際に職場や研究機関を訪問して仕事を体験する形式です。
多くの中学で取り組まれているため、高校生にはより実務に近い体験が期待されます。
あらかじめ体験する職業について調べ、質問や見学のポイントを考えておく事前学習や、活動後に自分の将来と照らし合わせる事後活動を必要とします。
まとめ
今回は、高校生のキャリア教育の目標・内容・課題と、身に付く力について説明してきました。
キャリア教育という言葉自体は、平成11年から世の中に出てきたものの、その重要性を教員が意識できていないという点や、転職や失業などに関するもしもの時の情報が提供されていない点は今後の課題となっています。
また、キャリア教育が行われる場面で紹介したように、新しいことを入れ込む必要は無く、普段の教育活動にキャリア教育の視点を盛り込むことで、生徒に社会人としての態度や意識を身に付けさせることが大切です。
進路指導に偏ることなく、生徒の実態に合わせて授業形式を選択する必要があります。
外部と連携した授業形式は、生徒にとって働くことを強く意識できるキャリア教育の方法です。
出前授業どっとこむでは、対象学年を選択し、どんな学びを提供してほしいのかを選択するだけで、最適な授業を提供するパッケージを調べることができます。
これから、高校生に向けたキャリア教育を実践する方は参考にしてみてください。