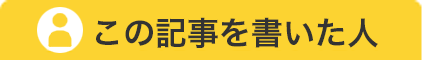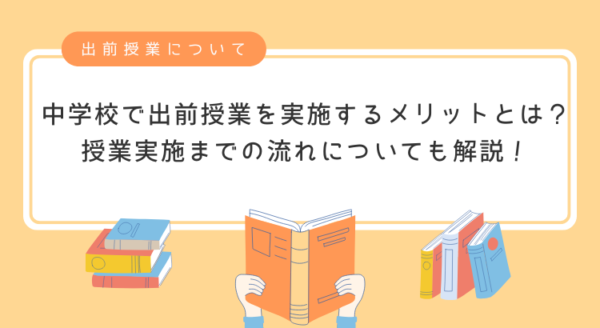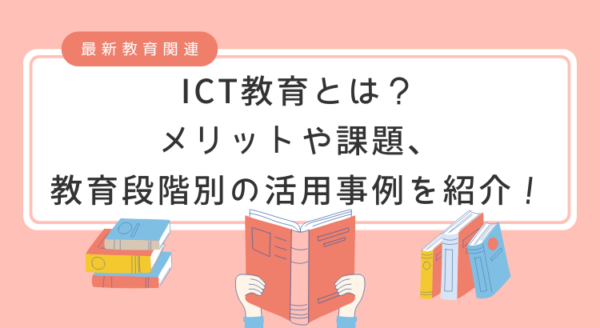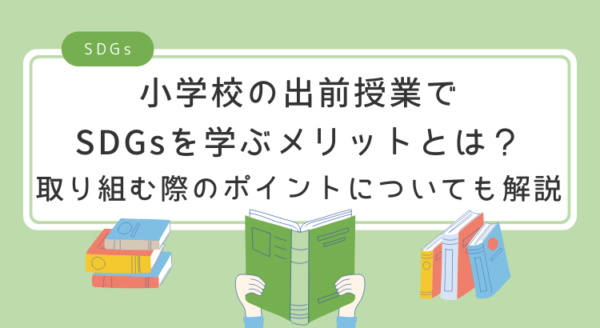
SDGsとは、環境劣化や貧困など人類が直面する問題の解決を目指す取り組みです。
SDGsの目標を達成するためには次世代を担う子どもたちへの教育と啓蒙が必要不可欠であり、実際小学校ではSDGsの学習が行われています。
では、小学生はどのようにSDGsを学べばよいのでしょうか。
今回は、小学生がSDGsを学ぶメリットとその方法、SDGs学習に取り組む際のポイントを解説します。
SDGsとは?
SDGsとは日本語で「持続可能な開発目標」という意味で、社会問題や環境問題の解決に向けて国連が定めた国際的な枠組みです。
2015年9月に開催した「国連持続化可能な開発に関するサミット」で採択されたことがきっかけで、目標達成に向けた取り組みが始まりました。
SDGsは全部で17の目標を定めており、具体的には以下のとおりです。
- 貧困をなくす
- 飢餓をなくす
- すべての人々の健康的な生活を確保する
- 質の高い教育が全員受けられるようにする
- ジェンダー平等推進と女性の地位を向上させる
- 安全な水とトイレを世界中に用意する
- エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
- 仕事にやりがいが感じられる
- 災害に強いインフラを確立する
- 人々や国の不平等をなくす
- 住み続けられる街づくりをする
- リサイクルできる仕組みづくりをする
- 気候変動に具体的な対策をする
- 海洋資源を保全して海の豊かさを守る
- 環境に配慮した取り組みをする
- 平和な世の中にする
- 異なる組織や個人同士が手を取り合って協力する
参考:国際連合広報センター|SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは? 17の目標ごとの説明、事実と数字
上記の目標を参考にし、SDGsが何を目指しているかを確認してください。
SDGsを学ぶと得られるメリット
SDGsへの取り組みをすると、児童は2つのメリットが得られます。
- 児童が将来過ごしやすい世の中になる
- 多くの人とコミュニケーションを取るきっかけになる
それぞれのメリットを参考にし、児童にどのようなメリットがあるのか理解を深めましょう。
児童が将来過ごしやすい世の中になる
SDGsへ取り組むと、児童が将来過ごしやすい世の中になります。
世界中では毎年のように水害の発生や地球温暖化の影響により食物が育たなくなるなどの問題が発生しています。
例えば、温暖化が進んだら毎日暑さに耐え続けなければなりません。
状況によっては、日本でも食物が育たなくなり、満足できるほどお腹を満たせない時代が到来する恐れがあります。
児童が過ごしやすい世の中を作りあげるためにも、小学生のうちからSDGsに関する学びを深めておく必要があります。
多くの人とコミュニケーションを取るきっかけになる
SDGsへの取り組みをすると、多くの人とコミュニケーションを取るきっかけになります。
どのような取り組みをすればSDGsで掲げた目標を達成できるかを周囲と相談することで、新たな考えが育まれるためです。
多くの人とコミュニケーションを取るきっかけがあれば協調性が高まっていき、周囲の人々と円滑に物事を解決するための思考力が身につきます。
SDGsを実現するために出前授業を小学校で使おう
小学校でSDGs教育を実施する際に、出前授業を活用するのも一つの方法です。
出前授業とは、学校に企業や専門家が訪問して児童に特定のテーマに関する授業をするプログラムです。
出前授業でおすすめのSDGsに関するプログラムの例として、4つをご紹介します。
- 木材で遊ぶ
- サステナブルな社会を変える
- しいたけの栽培体験から食材ロスを考える
- 謎解きを通して海のSDGsを学べる
それぞれのプログラムを参考にし、どのような授業を児童へ受けてほしいかを決める判断材料にしてください。
木材で遊ぶ
木材を取り扱う会社では、小学1年生と2年生向けとして木材で遊ぶことを通じて森と木材のつながりを学ぶプログラムを用意しています。
授業では、木はどこから来てどのように端材ができるかを学ぶことが可能です。
その後、ボンドやヤスリを使用せずに端材プールを作成し、森や自然への興味関心を育みます。
実際に木に触れて視覚や嗅覚、聴覚を活用しながら学ぶことで、木を身近に感じることが可能です。
サステナブルな社会を考える
古紙を取り扱う会社では、全学年を対象にゴミやリサイクルに関するグループワークも含めた授業をしています。
講師と共にゴミの処理方法やリサイクル方法などを知って理解を深めていき、自分たちが今から取り組めることは何かを考えます。
グループワークで意見を交わしながら考えることで、異なる意見を取り入れる柔軟な考え方を養うことや多角的視点を取り入れることが可能です。
しいたけの栽培体験から食材ロスを考える
食育プログラムを展開している一般社団法人では、全学年を対象にしいたけの栽培体験を通して健康問題や食品ロスに触れてSDGsに関して考えるきっかけを作っています。
しいたけの栽培方法や収穫のポイント、簡単レシピを学ぶことが可能です。
謎解きを通して海のSDGsを学べる
謎解きゲームを活用して海洋問題への興味を高めつつ、基本的な知識を学ぶことができる授業もあります。
また、オンラインで水族館とつないで特別授業をすることで、館長から水族館ならではの話が聞くことができるなど、現地の海から生中継することによって、リアルな海洋問題に触れることが可能です。
小学校で出前授業をするためのポイント
小学校で出前授業をするためには、2つのポイントに注意してください。
- 児童の関心を探る
- 学んだ内容を復習する時間を設ける
小学校で出前授業をするためのポイントを把握しておけば、児童たちがSDGsに関して理解を深めるきっかけになります。
それぞれのポイントを参考にしたうえで、出前授業でSDGsに関する学びを深めるきっかけを作りましょう。
児童の関心を探る
小学校で出前授業をする際は、児童の関心を探りましょう。
児童が興味のない授業をしたとしても、自らSDGsに関して学ぼうとは思いません。
例えば、海の生物に関して学ぶとしても、ゲームを用いて授業をした方が児童に興味を持ってもらいやすいです。
小学生が興味を持ちそうな内容を交えて説明し、授業の内容に興味を持ってもらう工夫をしてください。
学んだ内容を復習する時間を設ける
小学校で出前授業をする場合は、学んだ内容を復習する時間を設けましょう。
SDGsに関する知識を習得したとしても、忘れてしまっては意味がありません。
繰り返し復習する時間を設ければ何を学んだかの再確認ができ、SDGsの理解を深めるきっかけにつながります。
出前授業どっとこむを活用してSDGsを学ぼう
小学校でSDGsの出前授業をすると、児童が将来過ごしやすい世の中になることや多くの人々とコミュニケーションを取るきっかけができることなどのメリットが得られます。
また、出前授業どっとこむでは、SDGsに関する出前授業を数多く用意しています。
本記事を読んで興味を持った方は、ぜひお問い合わせください。