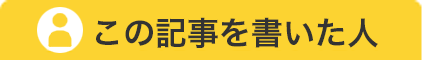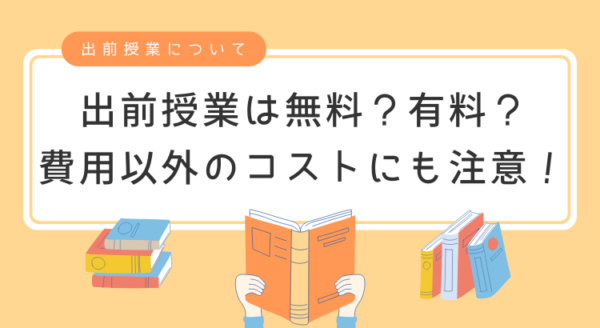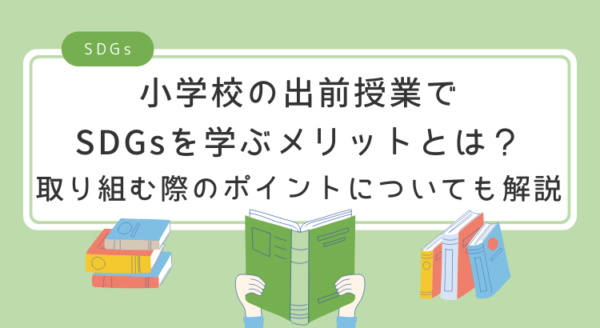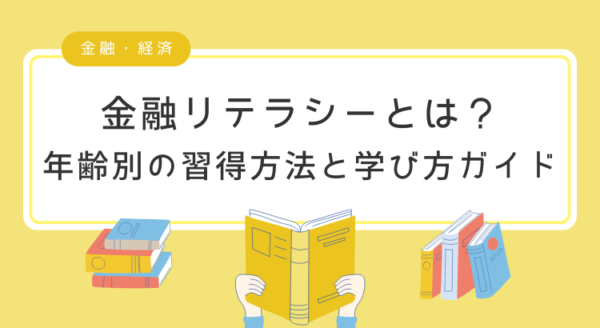
金融リテラシーとは、「お金や金融に関する知識やスキルを持ち、それを活用して適切な意思決定ができる能力」ということを指します。
金融リテラシーを学生時代から習得しておけば、将来的に金融トラブルに巻き込まれないための対策や適切な資産運用の方法などが理解できます。
しかし、どのように児童・生徒に金融リテラシーを習得させればよいかがわからないという方も多いでしょう。
今回は、金融リテラシーの年齢別の学習方法を解説します。
児童・生徒に金融リテラシーを学ばせたいとお考えの教育関係者は、本記事を参考にしてください。
金融リテラシーとは?
金融リテラシーとは、お金に関する知識や判断力を身に着けることです。
金融リテラシーは経済的に自立するために必要な能力で、金融商品での資産形成やお金の使い過ぎによる生活の困窮の回避ができます。
金融リテラシーを身につければ自分の収入に見合った計画的な支出ができるため、無理のない生活設計ができます。
今後児童・生徒が大人になると生活設計や資産形成、クレジットカードの使用などお金に関する選択が必要になる場面が多々発生するでしょう。
金融リテラシーを身に着けていれば、このような場面で最適な選択がしやすくなります。
お金のトラブルから身を守ることや適切な生活設計、資産形成のためにも、金融リテラシーの習得は大切です。
金融リテラシーを学ぶことが重要な理由
金融リテラシーを学ぶことが重要な理由として、3つ挙げられます。
- ライフスタイルの多様化
- 成年年齢の引き下げ
- 金融環境の変化
かつては、会社に入ると年を重ねるとともに給料が上がっていき、定年まで同じ会社で勤め上げることが一般的でした。
しかし、近年では同じ会社で働き続けるのではなく、別の会社へ転職する人が多いです。
また、2022年4月1日以降から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成人年齢の引き下げによって、18歳からクレジットカードを作ることやローンを組むことができるようになりました。
このような背景もあり、早いうちから金融リテラシーを学ぶ必要があります。
さらに、数十年前までは銀行に預けた時の金利が1%を超えていましたが、2024年11月現在は0.1%以下です。
働く以外にお金を稼ぐ選択肢として、投資を検討する人が増加してます。
上記の3つの理由から金融リテラシーを身に付ける必要性が高まっています。
金融リテラシーに関する授業を始められる時期
金融リテラシーに関する授業は、小学生低学年から始められます。
小学生低学年になると、レジでお金を支払うことに興味をもつ子どもが増えていくためです。
ただ、お金の仕組みに関して子どもへ一方的に話すと、興味が薄れる恐れがあります。
そのため、子ども自身がお金について考える時間を設けましょう。
学年別の金融リテラシーの習得方法
ここでは、小学校、中学校、高校に分けて、金融リテラシーの学習方法をご紹介します。
段階別の金融リテラシーの習得方法を学べば、自身が教えている児童・生徒へ適切な教育がしやすくなります。
なお、金融経済教育推進会議で作成された金融リテラシー・マップをもとに習得方法を紹介しているため、参考にしてください。
参考:金融経済教育推進会|金融リテラシー・マップ
小学生低学年
小学生低学年では、ものには価値があることを知り、ものを大切に使う習慣を身につける時期だと定められています。
例えば、お小遣いを計画的に使ってみましょう。
お小遣いの使い方を計画してみれば、将来的にお金を大切に使う習慣の形成へとつながります。
目の前の欲しいものを購入してしまう性格のまま大人になってしまうと、資金形成ができずに金銭的に困窮してしまうかもしれません。
お小遣いをすべて使い切る性格の児童には少しずつお金を貯めれば、もっと欲しいものが購入できるかもしれないと伝えましょう。
小学生低学年では、未来を想像したお金の使い方を教えてください。
小学生中学年
小学生中学年では働くことの喜びと大変さ、お金の価値の重さを理解する時期です。
例えば、社会で働いている人を職場見学で目の当たりにすることで、どのようにお金を稼げるかが理解しやすくなります。
働いている人に仕事でのやりがいや大変なことを実際に聞くことで、お金を稼ぐことがいかに大変か理解できます。
お金の価値の重さの理解によって、計画的にお金を使うことの大切さを学べるでしょう。
小学生高学年
小学生高学年では、ものの選び方や買い方を考えて適切に購入する能力を身につける時期です。
適切に購入する能力を身につければ、無駄遣いを防げます。
また、お金にまつわるトラブルは家族に迷惑をかけることを理解するとよいでしょう。
そのためには金融トラブルの事例を教え、適切な予防法を考えさせましょう。
金融トラブル事例の把握が、お金を適切に使用する習慣の形成へとつながります。
中学生
中学生は、金融と生活のかかわりについて適切に理解し、将来の自立に向けた力を養う時期です。
例えば、企業に労働力を提供して家計は対価として収入を得ることを学べば、将来どのように生計を立てていけばよいか理解できます。
ただ、老後のために貯蓄をする必要があるため、得た収入をすべて支出してよいわけではありません。
定年までにどれくらいの貯蓄が必要かを理解し、得た収入を計画的に使ってほしいことを生徒たちへ伝えましょう。
高校生
高校生では、社会人として自立するために基礎的な能力を養う時期です。
例えば、アルバイトや職場見学などでお金を稼ぐ大変さを身をもって体験することで、無駄遣いをしないように心がけられます。
また、現在の自分の教育や生活に支払われている費用を理解すれば、必要な支出を考えるきっかけになります。
出前授業で学べる金融リテラシー
出前授業とは、企業が講師として学校に訪問して特定のテーマに関する授業をする方法です。
出前授業どっとこむでは多数の金融リテラシーに関する授業を用意していますが、今回は代表して3つの授業をご紹介します。
- 投資を学習する
- お金につまずかないための教育をする
- カードゲームで金融に関する勉強ができる
それぞれの授業を参考にし、金融リテラシーを学びましょう。
投資を学習する
資産運用を取り扱う会社では、小学5年生〜中学3年生までを対象にクイズを通して投資と社会の仕組みを学べるプログラムを用意しています。
投資が自分や社会全体をさらに良くする仕組みだと理解し、人と社会とのつながりを学んで当事者意識を育むことが可能です。
投資方法とリスクを学べるため、金融リテラシーを養いつつ自分に合った選択をするためのサポートができます。
お金につまずかないための教育をする
金融経済教育セミナーを開催している団体では、中学1年生〜高校3年生までを対象に将来発生する可能性があるお金の困りごとを事前に学べるプログラムを用意しています。
例えば、マルチ商法の具体的事例を学びつつ、被害に遭わないための対策を学ぶことが可能です。
金融トラブルの手口や対策を把握しておけば、被害者や加害者にもならずに済みます。
ほかにも生活設計や家計管理に関する知識を学べます。
生徒たちがお金に困らずに日常生活を送るために把握しておいた方がよい知識を短時間で養うことが可能です。
カードゲームで金融に関する勉強ができる
金融教育の専門会社では、中学3年生〜高校3年生までを対象に楽しみながら金融を学べるプログラムを用意しています。
お金の必要性を理解した後に、カードゲームを活用してどのような将来を歩んでいくかを模擬体験できます。
カードゲームを活用して金融の授業ができるため、生徒たちが集中して授業を受けることが可能です。
また資産形成や投資の基本を学び、仕事をする以外にお金を増やす方法を学べます。
出前授業どっとこむで金融リテラシーを習得しよう
金融リテラシーは、ライフスタイルの多様化や金融環境の変化、成年年齢の引き下げなどさまざまな理由から学ぶ必要があります。
また出前授業どっとこむでは、金融リテラシーを学べる授業を数多く用意しています。
本記事でご紹介した事例を参考にし、金融リテラシーを出前授業で学びましょう。