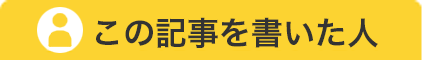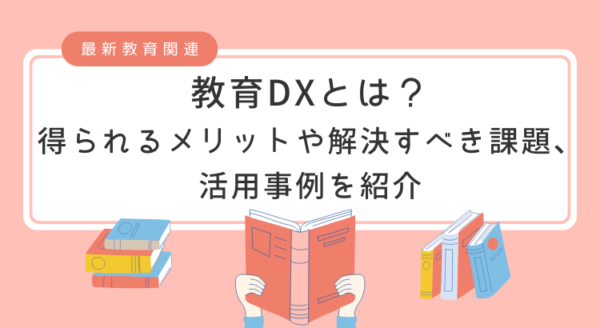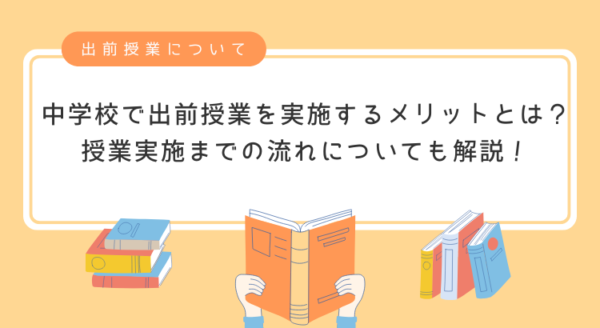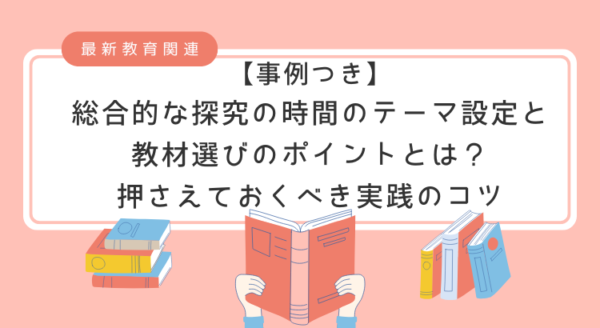
文部科学省の学習指導要領の改訂により、近年ますます注目されているのが「総合的な探究の時間」です。従来の「総合的な学習の時間」から進化したこの時間は、生徒の主体性を育み、社会とのつながりを意識した学びを実現することを目的としています。
しかし実際には、「テーマ設定に悩む」「教材が見つからない」「探究活動の評価が難しい」といった声も多く、教育現場では試行錯誤が続いているのが実情です。
この記事では、教育現場で実践的に役立つ「総合的な探究の時間」のテーマ設定や教材選びのポイントを中心に、成功事例や具体的な導入方法まで詳しく解説します。具体例を交えながらご紹介しますので、これから探究学習を深めたい教育関係者の方はぜひ参考にしてください。
総合的な探究の時間とは?基本的な考え方を再確認
「総合的な探究の時間」とは、生徒が自ら課題を見つけ、情報を収集・整理・分析し、考察・表現する過程を通じて、問題解決能力や主体的に学ぶ姿勢を育てることを目的としています。
ここで大切なのは「正解を覚えること」ではなく、「正解がひとつではない問いに向き合うこと」です。例えば、「地球温暖化の原因は?」ではなく、「温暖化を食い止めるために私たちにできることは?」と問いを変えることで生徒が自分ごととして考えるようになります。
さらに、この学びは個人の思考にとどまらず、仲間と意見や情報を出し合うグループワークやディスカッションなどを通じて進める「協働的な学び」が不可欠です。こうした活動によって、多様な視点や情報が結びつき、課題の理解が深まり、より実践的で多面的な探究へと発展していきます。
探究学習・教科学習・調べ学習の違いとは?
| 学習の種類 | 特徴 |
| 探究学習 | 「問い」を自分で立てて、考えながら学びを深めていく。仮説や対話、試行錯誤が大事。 |
| 教科学習 | 国語や理科など、決められた教科の内容を学ぶ。知識の基礎をつくる時間。 |
| 調べ学習 | 情報を集めてまとめる活動。レポートや発表などが多い。 |
探究学習は上記の通り、生徒自ら学習に取り組むプロセスを重視し、主体性や考え抜く力、協働的な学びを促すのが特徴です。
一方、教科学習は国語や数学など既定の教科に基づき、知識や技能を習得するための学習です。教師主導で体系的に進められるため、学力の基礎を支える役割を担います。
調べ学習は、テーマに関する情報を収集してまとめる活動ですが、探究学習のように課題の設定や深い考察、仮説検証までは求められないことが多いです。探究学習は、これらの学びを統合しながら、より高次な学びへと導く教育活動といえます。
例えば、「食品ロス」をテーマにした場合、それぞれの学習は次のように進められます。
| 学習の種類 | 具体例 |
| 探究学習 | 「学校の給食で出る残飯をどう減らせるか?」など、自ら問いを立ててアンケートをとり、改善策を実践・提案する |
| 教科学習 | ・家庭科で「食品の保存方法」を学ぶ ・社会科で「日本の食料自給率」を調べる |
| 調べ学習 | 日本でどれくらい食品が捨てられているかを調べ、レポートにまとめる |
この違いを意識することで、「探究学習は生徒が主体になって動く学び」だと理解できます。
なぜ今、探究学習に取り組む必要があるのか?
社会の変化が加速する現代において、単に知識を蓄積するだけでなく、自ら課題を見つけ、考え、行動する力、正解のない課題に挑む力が求められています。AIやグローバル化の進展により、予測不能な時代に突入した今、教育現場では「生きる力」や「思考力・判断力・表現力」を育む学びが不可欠です。
探究学習は、知識の習得にとどまらず、自ら問いを立て、情報を収集・分析しながら解決に向けて考え抜く過程を通じて、生徒の主体性や創造性、協働的な姿勢を育てることができます。こうした力は、これからの社会で必要とされる「生きる力」そのものであり、そのため、探究学習は新しい学びの中心として重視されているのです。
テーマ設定の重要性と成功のカギ
探究学習を成功させるカギは「テーマ設定」です。魅力的で深い学びにつながるテーマを選ぶことが、生徒の意欲を高め、学びを継続させる原動力になります。
良いテーマ設定の条件とは?
- 生徒が興味を持てる
- 社会や地域とのつながりがある
- 答えが一つではなく、課題解決に向けた思考を深められる
- 学年や学校の特色に合っている
テーマ設定の具体例
テーマ:AI時代の働き方とは?
高校生は進路やキャリアを意識する時期なので、将来の社会を見据えたテーマが効果的です。AIが普及する中で「なくなる仕事」「新しく生まれる仕事」を調べ、自分のキャリアと結びつけて考える活動は、自己理解や進路選択の手がかりになります。
教材例:AIに関するニュース記事、職業インタビュー、労働市場の調査データ
テーマ設定に困ったら?
以下の方法でヒントを得ることができます。
- SDGs(持続可能な開発目標)から考える
- 地域の課題をヒントにする
- 実践例を調べて応用する
特にSDGsは探究学習との親和性が高く、「飢餓をゼロに」「ジェンダー平等を実現しよう」など、世界的な課題をローカルな視点で考えるきっかけになります。
教材選びの工夫と実践ポイント
テーマが決まった後に重要になるのが「教材選び」です。ここでの教材とは、教科書のような一律のものではなく、調査や議論、発表のために使える情報源やツール全般を指します。
よく使われる教材の種類と使い方
- 新聞・ニュース記事
時事問題や社会課題を扱う際に有効です。記事を要約する練習にもなります。
- 動画・インタビュー映像
多角的な視点を得るのに役立ちます。映像教材は感情に訴える力もあります。
- ワークシート・ワークブック
思考の整理、情報の記録、グループ討議などに活用されます。
- オンラインツール
Googleフォームを活用したアンケート、MiroやJamboardでの共同作業、生成AIツールでのアイデア発散など、ICT活用も教材の一部です。
教材を選ぶ際の注意点
教材を選ぶ際は、以下の三点を意識しましょう。
- 生徒の発達段階に適した内容か
- 情報の信頼性が高いか
- 生徒に多様な視点を提供できるか
また、単に教材を与えるのではなく、生徒が自ら情報を選び、分析し、活用するという視点を忘れないことが重要です。
実際の実践事例
ここでは、総合的な探究の時間の事例をご紹介します。
テーマ:「空き家問題を解決して町を元気にしよう」(高校2年生)
活動の流れ
- 地域の空き家に関する現状を調査
- 役所職員や地域住民にインタビュー
- 解決策を考え、プレゼン資料を作成
- 地元のまちづくり会議で発表
成果と変化
- 生徒の地域への関心が高まった
- 発信する力(プレゼンテーション能力)が向上した
- 実際に地元自治体との連携へと発展
このような活動を成功させるには、外部とのつながり(地域・企業・専門家)を意識的に取り入れることが大きなカギとなります。また、探究の過程で「問いを深める」「仲間と対話する」ことの重要性も見えてきます。
教育関係者が抱える課題と解決のヒント
評価方法や、探究学習の時間の確保など、探究活動を支える立場の教員にとっても、いくつかの課題があります。
これらを解決するには、指導の「型」や「支援ツール」を活用することが有効です。例えば、学習活動のプロセスを可視化するルーブリック評価の導入や、学校全体でテーマを統一して展開するなどの工夫が考えられます。
ルーブリックとは、学習到達度を示す評価基準を、観点と尺度からなる表で示したものであり、ルーブリ ックを用いて行う評価方法をルーブリック 評価といいます。
参考:文部科学省|ルーブリック評価の活用によるキャリア教育の推進
例えば、以下のように表にしておくと、生徒も「何を目指せばよいのか」がわかりやすくなります。
・観点:調査の工夫、発表のわかりやすさ、仲間との協力
・段階:十分できた、ある程度できた、できていない
探究活動を支援する教材やプログラムの活用
「準備が大変…」というお悩みを持つ方もいらっしゃるでしょう。近年では、教育現場をサポートするための探究学習専用教材やプログラムが数多く提供されています。
- SDGsやキャリア教育をテーマにした探究教材
- オンラインで完結する探究教材
- 企業や団体による出前授業
これらをうまく取り入れることで、準備の負担軽減や学びの質の向上を図ることが可能です。
探究の質を高めるには“つながり”が鍵
総合的な探究の時間は、単なる自由研究ではなく、生徒の将来を見据えた「生きる力」を育む大切な時間です。だからこそ、テーマをじっくり選び、教材も工夫しながら、地域の人や企業、専門家とのつながりを活かすことが大切です。
出前授業どっとこむには、探究活動をサポートする企業や団体のプログラムが多数掲載されています。授業作りのヒントにぜひ活用してみてくださいね。